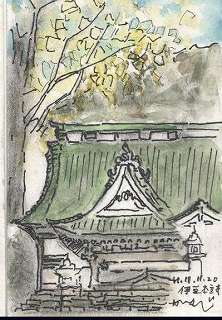
|
日蓮大聖人伊東の浦へ御法難の翌1261年江川家十六代当主江川太郎
左衛門義久公の懇請に応じ当地韮山へ遊化された。義久公はじめ村人達も
悉く信伏随従す。義久公の子英友公は遺命により剃髪し本立院と号し邸内
に大乗庵を建立した。その後1506年江川家24代当主英盛公が邸内にあった
大乗庵を当地に移し本立寺を建立す。のち宗門の学匠として知られる日澄
上人韮山に布教せる秋、経塚の霊蹟を参拝大堂を建立し日法上人手ぼりの
高祖尊像を奉安し日澄上人により開山の法式を挙げ当国中央の根本法華道場
として大成山本立寺と称し宗門本山の礎を長くこの所にとどめる。江川邸の
旧跡とともに参拝する者日々多く永く法灯を今に伝える。

|
本山は興統富士門流に属し東光山と称して本門七本山のひとつにかぞえらて
来た名刹。当山は1299年日興尊師の経講義の際、聴聞をおろそかにしたとして
破門された日尊上人が御勘気を解くべく始めた諸国遍歴の第一歩として正安
3年1301年4月に建立された寺であり言わば上人の東国弘教初転法輪の道場たる
由緒ある寺である。その諸国遍歴のたびは十有二年奥州津軽から鎮西に及び
幾百千里に及び新寺建立は36か寺に及んだという。そして以来42世を数えている。
其の奉祀する所の宗祖御尊像は上人が12年間肌身はなさず給仕し給う霊像にて
人呼んで「笈の御影」と称し奉る。

|
当山は至徳3年1386年日什上人が土地の豪族佐原常慶及び内藤金平
両氏の外護によって開基された霊場である。山号を延兼山と称し京都の
「妙満寺」を総本山とする所謂妙満寺派に属する別格本山であり、S16年
に日蓮宗の門下各派が合同しため身延山を総本山とする日蓮宗に所属
してその一本山となった。
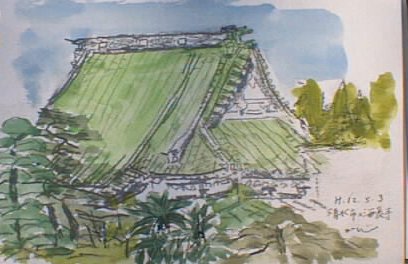
|
当山は1120年前平安朝文徳天皇の852年に創設された天台宗の古刹峨岳寺
としょうしたものが前身である。がその270年後鎌倉時代日位上人が
この地を弘教のおり寺主、慈証尊者と法義問答し帰伏させた。これより
当山は一山を挙げて本化門下となり慈証は日受と法号を改め日位尊者を開基と
仰ぎ昼夜聴講、待座した。

|
当山はもと駿州松野村にあったもので6老僧日持上人がその開山である。
日持上人が中国大陸の布教に出立されてから無住同様の寺となり荒廃した。
徳川家康の側室お万の方はこれを嘆き家康に請うて元和元年
(1615年)駿府城の東北の鎮護の道場としてこの地を移し再興した。
これには身延山21世日乾上人の勧めがあったと言われている。
尚この寺には勝安房代々の墓、佐久間象山の室の墓もある。